こんにちは、にわです。
こども園生活振り返り投稿は一旦これで終了の予定ですが、今回は、「卒対」について。
目次
「卒対」とは?
概要
「卒業対策委員(会)」の略だそうです。(インターネットの様々なサイトより)
マ友・パパ友もおらず、育児経験のない我が家は、園から配付されたプリントに記載されていた「卒対」という言葉の意味がわからず、インターネットで検索しました。バックグラウンドが異なる複数名向けの比較的正式な配付物で、略語を使わないでほしいです…。
調べてみると、ワイドショーのでみるような不穏な情報がたくさん出てきました。これから役員決めでどうしようか…と不安に思われている、去年の夫と私のような方々の参考になればと思い、我が家の体験したこと、思ったことなどを記録したいと思います。
卒園アルバム係
仕事内容・負荷

と私は思っていたのですが、園から配付されたプリントに記載されている必要人数が多いことに疑問を感じて、改めてインターネットを検索。

ページの割り振りやらコラージュやら、子どもごとに写真数が偏らないように配慮したり、卒対係の中でもっとも時間がかかるようです。(息子の園の過去実績より)
対応期間
開始時期は、役員決めがおわった直後から、顔合わせや、誰が何を担当するだとか、どんな係がそもそも必要なのかなど、人数が多いと作業は分担できるのかもしれませんが、調整事に時間がとられます。
そして、「卒園アルバム」だけに、卒園式の写真もアルバムに含める関係上、アルバムの出来上がりは、卒園後、引き渡し完了はなんと夏頃!ということで、卒園後も仕事を抱えた状態となります。
我が家が立候補しなかった理由
そもそもの仕事内容がたいへんであるとの情報に加えて、卒園後も抱えているモノが残る、という点が一番のネックでした。
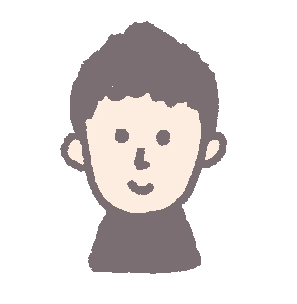
と夫と話し、アルバム係は無理、という結論に至りました。
文集係
仕事内容・負荷
まだ字を書けない子もいるのに

と疑問でしたが、1ページ1園児/先生で、将来の夢とか、好きな給食とか、園の思い出とかいったいくつかの質問と、回答を書く吹き出しを割り付けたページを準備して、各自記入・提出してもらったものを製本する、といったものでした。
todo
- いつまでに何をするのか?(全体のスケジュール)
- 質問事項はどうするか?
- ページのレイアウトはどうするか?
- デザインはどうするか?
- 個人ページ以外は何を掲載するか?
- どこの業者に依頼するか?
- 予算はいくら使えるのか?
- 誰がどの役割を担当するか?
(園とのやり取り係・業者選定係・業者とのやり取り係・デザイン係・用紙の配付と収集係など)
夫によると、このあたりが、当初、集まって話し合われた項目です。
方向性とそれぞれの担当さえ決まれば、あとはコロナということもあり、LINEなどを使ってリモートでやり取りしていましたが、なんだかんだ、5,6回は会議のために園に出向いていました。(夫が)
対応期間
息子が年長となった年は、コロナで4,5月は通園がなかったため、役員決めも6月に入ってからだったと記憶しています。例年より開始時期が遅かったこともあり、役員決め直後から、活動は始まりました。
製本業者に見本刷りの依頼をしたのが年末で、文集といっても、写真もふんだんに使われていたため、画質がおかしいところや、レイアウトの微修正などをして、完成品の数十冊分の依頼を業者に出したのは、年明けでした。
途中のもめている状況をみていたため…年明けに無事発注できた、というのは、優秀だったと思います。完成品は卒園式の日に配付されましたが、実質、業者に依頼したところで、
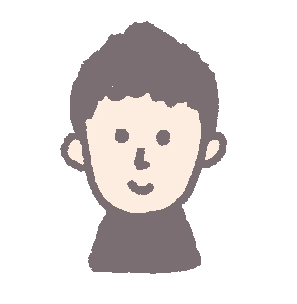
という気分になれ、スッキリした気持ちで卒園式に参加できました。
我が家が立候補した理由
完全に消去法です。これ以外に

それだけです…。
謝恩会係
仕事内容・負荷
コロナ禍では、役員をやりたくないモチベーションの低い保護者にとっては、謝恩会係もありだったかもしれません。(逆に、謝恩会がたのしみだった!という方にとっては残念な年であったと思います。)
例年は、園児・先生・保護者参加の飲食パーティーのようなものが行われ、その会場探しや、余興の企画など、我が家にはまったくもって適性のない任務の遂行が必要でしたが、今年は園児と先生が園内で写真のスライドをみておわり、という簡素なものでした。
今年の謝恩会係のみなさんは、おそらく写真を収集して、動画仕立てに写真のスライドを音楽に乗せて構成しておわり、という感じだったようです。
対応期間
例年通りの対応が必要な場合は、役員決め直後から、謝恩会まで、けっこうな期間対応が必要だったのでは…と想像します。
我が家が立候補しなかった理由
夫も私も、完全に適性がない、という自覚のもと、謝恩会係はコロナ禍といえども検討外でした。
その他の係
年長では、卒対役員のほか、年少や年中時同様、通常のクラス委員も、もちろんあります。年少・年中のいずれかで役員を担当した人は、年長では、卒対役員もクラス役員も免除、というシステムでした。
ここでようやく、年少・年中で役員に立候補した人たちがいた理由を知った、無知な夫と私…。子育てブログなどを拝見していると、やりたくて役員をやっている方もいるようですが、息子の通った園では、やりたくてやっている、という感じの方はまったくいませんでした。
みなさん卒対を逃れるために、年少・年中で役員に立候補していたようです。結局、年長では、役員経験のない保護者の8割以上が、何らかの役員をやることになりました。
我が家が経験した文集係
メイン担当であった夫の感想
ポジ/Pros
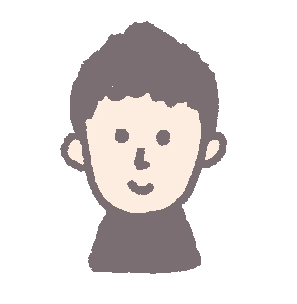
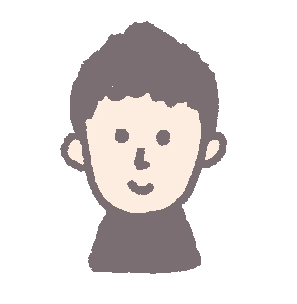
ネガ/Cons
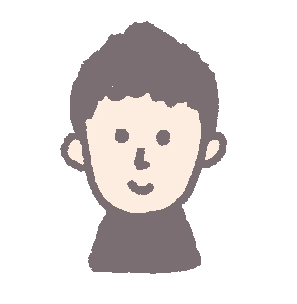
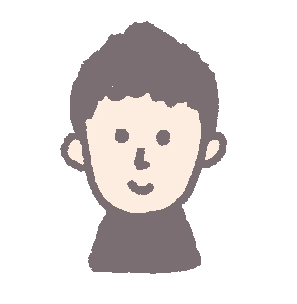
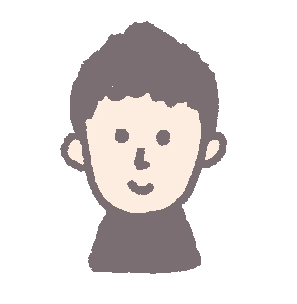
夫がやったこと
done
- 文集係メンバとして会議類への参加
- 業者最終選定
- 紙で収集したデータのデジタル化
- メンバがデータを保存するためのプラットフォーム準備
- メンバが個別に作成したデータの管理
- 冊子の構成
- 著作権等の問い合わせ
- 完成品の試し刷り発注
私がやったこと
done
- 業者候補探し
- 業者候補を4つまで絞ってコストと特徴をまとめて提示(夫に)
- 業者候補からサンプルを取り寄せて仕上がり感を提示(夫に)
- 企画のサポート(夫にアイデア提供)
当初は、前年踏襲で、毎年依頼している印刷業者に発注する方向で話が進んでいましたが、30-40年前の

と思えるようなクオリティの文集で、手に取ってもまったくワクワク感がない前年と前々年の文集をみて、フォトブックやフォトプリントの業者を探しました。コスト的にも例年の半額で、フルカラーで期待した感じの文集に仕上がりました。
いろいろ夫に意見を聞かれ、応答しては却下されたため、その他はとくに手伝いませんでしたが…前年踏襲を打ち破って、前年より低コスト高品質の文集が完成したことに、すこしは貢献できたはず…。
フォトブック業者はたくさんありますが、予算やサイズやページ数などのさまざな制約をチェックしていくことで、自然と5つ以内程度まで絞られていきます。そこそこ時間は使いましたが、こういう作業であれば、仕事をしている人でも、休日を利用して対応することは可能です。
卒対や園役員に関して思うこと
問題点
仕事のようで仕事じゃない
仕事のようで仕事ではない、プライベートのようでプライベートではない、という点が、物事を進めにくいポイントだと感じます。
仕事であれば、自分の役割はおおよそ明確であり、組織のヒエラルキーやビジョンに従って従業員は行動するし、同僚たちは何が得意で何が不得意か把握しているし、決まらない物事については最終的に上層部の一声で決定することが可能だし、自分の立ち位置や為すべきことは明確です。
一方、園の委員会という組織では、係の中に1名でも心持ちの異なるメンバがいると、一気に物事の進捗が危うく、関係がいびつなものになる、園側も、保護者たちの集まりに、集会所を貸すなどの協力はしても、積極的な関与はしてこず、園に上司のような役割を求めることはできない、と観察していて感じました。
メンバ間のモチベーションの温度差
夫の担当した文集係は、全部で7,8名いたと思いますが、他の係がイヤで仕方なく立候補した我が家のようなタイプのメンバ(9割)と、全部やるよ!まかせて!というほどではないものの、それなりにモチベーションが高いメンバ(1割)という構成で、開始早々もめごとが発生していました。
みんなフンワリやんわり、卒なく揉め事なくおわらせたい、と思っているものとばかり思っていたのですが、初回の会合に参加できないと申し出たメンバに対する非難がすさまじくて驚きました。ワイドショーみたい…。
誰だって予定くらいあるだろうに…そんなに責めるようなことなのだろうか…と思うのは、私の熱意が足りないからなのか?
その衝突から、一気に役員のグループLINEのやりとりは不穏な空気をまとい、それが発端となり、リーダーを降りる降りないだの、揉め事がつづき、このまま空中分解では、と眺めていたら、途中で仲直りしたようで、表面上は「子供たちのためにがんばりましょう!」と進行していきました。
しかし、園で会ってもみなさん会話も交わさず、心から仲直りしていないのは一目瞭然で、

と思わされました。
メンバ間の性格の違い
てきぱききっちり進めたいメンバ(3-4割)と、のんびりベストエフォートで進めたいメンバ(6-7割)と、相性が非常に悪い…と感じました。
揉め事の発端となった会議も、絶対参加と思っている派と、その他の予定を変更してまでの参加は不要と思っている派と、強制力を持った人(上司)が存在しない組織運営の難しさを感じました。
役割が決まってからは、夫もいろいろと作業を持ち帰ってきていましたが、一向に対応を進める様子が見えないので、

間に合うの?
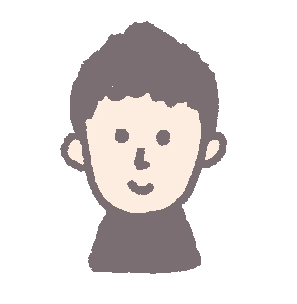
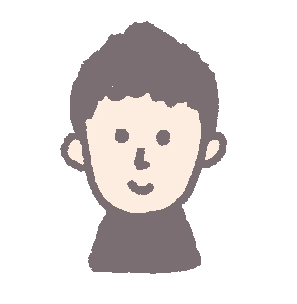
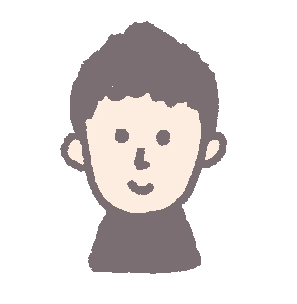
...といったのんびり加減で、夏休みの宿題は最初の1週間で全部おわらせる派の私からすると、

...とみていてイライラが募ってきましたが、最終的にはお役目を果たせたようで、ほっとしました。
提案・希望
園生活の4年で、役員制度には思うところがいろいろとありましたが、こうだったらいいのに…と思ったことを記録したいと思います。
その1:イベントごとにスポットで担当者を募って対応する
これは、息子の通った園では部分的に実施されていたことなのですが、役員はいるものの、役員だけでは手が足りないイベントについては、都度、ボランティアを募って、ボランティアの保護者たちがスポットで役員的仕事を担っていました。
ある程度余裕をもった日にちで事前に予定が提示されていれば、私も仕事を休むことができたため、近所の公園の遠足の引率等、息子の様子を見るよい機会なので、我が家も無理のないイベントについては、何度か立候補しました。
イベント時にほかの保護者より早く園や出先に出向き、いろいろな準備を手伝う、というのが、息子の通った園での役員の主な仕事でしたが、息子が通った園では、明らかにみなさん役員になることを避けており、役員決めは毎度微妙な空気となっていました。

と思ったものです。
予定が定まらない通年の対応は無理でも、年のうち何回か、スポットであれば対応できる、という保護者は少なくないと思います。
その2:お金で解決
息子の通った園は、保育か幼稚園かの先生を育てる専門学校と連携していたため、先生候補の学生さんたちが、保育実習にきたり、イベント時には、手伝いにきたりしていました。
これらは無償(あるいは学生さんたちにとっては授業の一環)だったと思いますが、保護者のボランティアが集まらない場合は、バイト代を払って学生さんたちに手伝ってもらうなり、スポットで対応してくれるサービスを利用するなり、

と言われても、歓迎する保護者は多いのではなかろうか。
みんながイヤイヤ役員をやるような状況ならば、お金で解決も選択肢の一つだと思います。コロナの今、健在なのかはわかりませんが、企業の運動会開催をサポートする会社、というのを以前テレビで見たことがあります。企画から当日の物の手配や進行まで、全部対応してくれて、社員は参加するだけ、というサービスです。
社員のエンゲージメント向上や、チームワーク形成のための福利厚生費で運動会を実施する企業の需要によりうまれたサービスとのことでした。こういったサービスはいろいろあると思うので、保護者の時間を奪わない運営について、園側も考えてほしいです。
我が家のように、完全なる専業主夫/主婦世帯なんて、もはやほぼいない、とくに子育て世帯ではほぼいない、そして今どき専業主夫/主婦世帯となることを選択している家庭は、おそらく我が家同様、なんらかの理由があり、園の役員仕事に手間暇たっぷりかけられる、という人はほぼいないだろうと思っています。
こんなにみんな嫌がっているのに、なぜ役員制度を続けているのか、疑問でなりません…。もちろん、やりたいという希少な保護者も多少はいらっしゃるのかと思いますが、お金で解決してもらいたい、と思っている層もそこそこいるのではなかろうか…。
我が家は、甥っ子にバイト代でも払って役員活動をしてもらおうかと考えたくらいです。
その3:1人担当制
作業の負担を軽減すること、より多くの保護者の意見を反映させること、1人に責任を負わせない、1人の自由にさせない等を目的としてチーム制を取っているのだと思いますが、私がもし係をやる必要があるのであれば、チーム制ではなく1人担当制を希望します。
チームであるがゆえに、会議などが必要になり、物事の決定に時間がかかり、お伺いや調整に多くの時間が費やされ、勤め人の参加は厳しくなります。意見の相違やいざこざがあれば、大きなストレスとなります。
そんなストレスを抱えるくらいであれば、そして役員活動のために貴重な有給休暇を消費しなくてはならないくらいであれば、全決定権を与えてもらえれば、1人ですべての作業をやってもよい、という人は、そこそこいると思います。
なんだか収拾がつかなくなってきてしまいましたが、現在、我が家は小学校での役員活動はどんなものなのか?に戦々恐々としています。園での経験のもと、低学年のうちに役員をすませて、あとはのんびりしたい…と考えているのですがどうなることか…。
2021年4月吉日